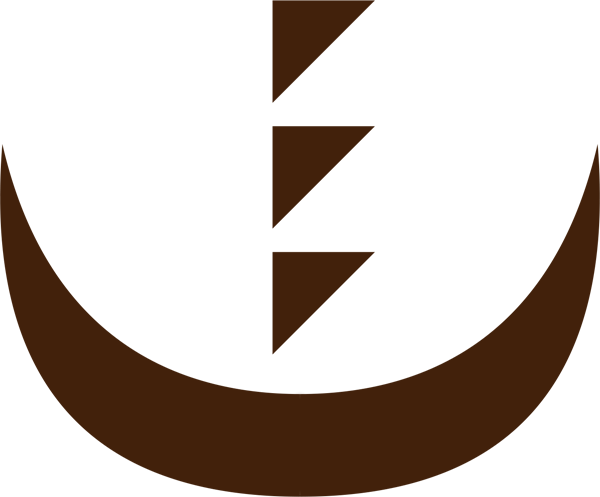home > uta-dan
uta-dan
2024.01.16

2023年12月10日 公開講座 アンケートへのコメント
改めまして、東京学芸大学公開講座「歌曲コンサートの今」にご参加くださり、誠にありがとうございました。その際にご協力いただきましたアンケートにて、質問をお寄せいただきましたため、10の質問について、回答をします。
なお、次回開催は 2024年9月頃 を予定しております。詳細は4月をお待ちください。
質問1
きれいな月も、冷たく見える月やあたたかく見える月もあり、自分(演奏者)と詩の中の感情が違うとき、どうしたらいいのかなという疑問が残りました。
石崎:
「自分」と「演奏者(もう一人の自分)」を別物と捉えて、「自分」は一旦置いておいて、「もう一人の自分」だったらこう感じる、演じるだろうなと切り離して考えて表現してみると面白いのかなと思いました。
森田:
演奏表現上の「私」とプライベートな「私」をどのように繋げるのかを考えると楽しいですよ。後者の「私」も一つではなく、先生としての私、夫としての私、演奏家としての私、就寝中の夢の世界の中にいると自覚している私、など。
質問2
先生方の選曲の基準を教えてください。基本的に好きな曲を選ばれていると思うのですが、例えば、曲は好きだけど詩に共感できないとき、どのようにアプローチされていますか。
石崎:
今回は「夜」というテーマを基に、「夜」に関連する曲を、作曲家毎に2~3曲ずつピックアップしました。最終的には森田先生の曲目と照らし合わせて、その時代や作曲家、曲の持つ雰囲気も絡めてプログラミングしました。また曲は好きだけど、詩は・・という場合(その逆も然り)も往々にしてありますが、質問1同様、「演奏者(もう一人の自分)」のキャラクターとして捉えて演奏しています(私の場合ですと、その「もう一人の自分」は、すでにその詩に対して共感している状態です!)。
森田:
「私がある曲を好き」になるのではなく、「ある曲が私に好きと思わせる何かを発している」と考えているかもしれません。
質問3
自分の声質や強みなどは、だいたいどのくらいで定まってくるのでしょうか。
石崎:
まず声質ですが、基本は生まれ持った「声帯」である程度は決まってしまうと思います。そして声質の判断材料にはパッサッジョの位置や日頃の訓練、そして舞台経験によっても変わってきますので、一概にいつとお答えするのは難しいですね。ちなみに「声帯」に関して興味があれば、声帯の専門医がいる耳鼻咽喉科で、一度ご自身の声帯を見てもらうのも良いかもしれません。例えば、バリトンである私がテノールに憧れていて、たとえ高音が出たとしても、声帯の厚みや長さ、また上記の判断材料を加味して(実際に専門医に伺ったうえで)、自分はバリトン(もしくはハイバリトン)である、というようなニュアンスです。あと「強み」に関してですが、主観的に捉えると、「強み」と「どれだけ好きで、その作品に心から没頭でき、自信を持つことができているか」は連動しているのではないかと思います。一方客観的に捉えると、どれだけそのジャンル(オペラか歌曲か、イタリアもの、ドイツものか等)のオファーが多いか、また求められているかという感じでしょうか。私の場合は、前者のケースでしたら20代前半で、客観的に捉えた場合は40代あたりで定まってきたのかなと感じています。
森田:
声種やそれぞれの身体によってかなり差があると思います。イタリアのオーソドックスな歌唱指導に則って学んだ場合、パッサッジョ(passaggio)で自分の声をどのようにコントロールするかを見ながら判断することが多いです。
質問4
ドイツ語からイタリア語へ移ったときの2言語の差や、特に気を付けたことを知りたいです。また、ピアノ伴奏の方も、ドイツ・イタリア語の違いやピアノの表現で意識したことを伴奏者の視点から教えてほしいです。
石崎:
プログラミングの観点からですが、一部の前半「イタリアの夜」では、トスティの中でも比較的ポピュラーな作品、後半「ドイツ・オーストリアの夜」では、ブラームスの定番な作品を並べたよく見かけるプログラミング。そして二部の前半「イタリアの夜」では、あくまでも主観ですが、どちらかといえばドイツ歌曲におけるプフィッツナーや20世紀の作品を彷彿させるピッツェッティやトッキのレパートリーが並び、後半「ドイツ・オーストリアの夜」でもコルンゴルトといった日本での上演は珍しい作品、シュトラウスにおいては比較的華美な作品を並べたプログラミングにしました。そして、それらがミックスされたとしても、一つのテーマを通して、歌曲コンサートとして一貫性のある、新しい形のプログラミングを心掛けました。特に気をつけたことは、異なる言語のプログラムにおいて言語差を感じさせないプログラミング、「詩」や「音楽」、そして韻律などの根底にある共通項を大切にしながら3人で作品を仕上げていったことでしょうか。
森田:
イタリアからの目線でドイツを眺め、「素敵な表現だな」とか「自分にはない表現だな」と素直に楽しめるマインドを大切にしました。またイタリアに関しては、イタリア人のメンタリティと、イタリア母語ではない演奏家個人の経験の接点を表現したいと努めました。
小田:
イタリアとドイツの歌曲の弾き分けは意識していることの1つです。自分なりの考えをいくつかの観点から書いてみたいと思います。
イタリアとドイツについて、彼らの文化に根付いている音や、発展のベースとなった音は、音作りのとても重要な参考になります。例えば、鍵盤楽器について言えば、チェンバロの音は、イタリアとドイツとで、随分と異なる響きになっています(フランスも大きく異なります)。そうした音を前提として、イタリアであればスカルラッティらが、ドイツであればバッハらが作曲の営みを行い、その歴史の延長に、今回演奏したトスティやピッツェッティ、またブラームスやR. シュトラウスがいるという整理は有益だと思います。作曲家たちが、どれほど意識的であったかどうかは分かりませんが、当時の楽器の音や、歌い手の声の特徴は、多少なりとも作曲行為に影響したと考えることが自然に思います。よりブラームスらしく、よりトスティらしく、という作曲家の頭で鳴っていたであろう響きを追い求めるならば、こうした「当時の音」という観点から、ピアノの音色の弾き分けを考えていくことは有効だと、個人的には考えています。その意味ではさらに、同じドイツ出身の作曲家だとしても、ブラームスとR. シュトラウスの演奏にも違いを考えていくことができると思います。
別の観点から、特に詩の観点から考えてみることも大切だと思います。アンサンブルピアニストは技術も知識も一流の人しかできないと言われるほどに難しいとされますが、その理由は、ピアノパート以外の音楽も熟知した上でピアノを弾かなければいけないからのように思います。特に詩への関心は、声楽のピアノを弾けるかどうかという意味で、大きな分かれ道になるかもしれません。
そもそも、イタリアとドイツの詩では、詩の作られ方が大きく異なります。イタリアの場合は、1詩行当たりの音節数が11であったり、7であったりですが、ドイツの場合は脚で数えていきますので、ヤンブスやダクトゥルスのような、脚の組合せによって詩が構成されます。このあたりは、説明し始めると長くなりますので割愛しますが、つまるところ詩の作られ方が違うということはリズムや詩のフレーズの質感も違います。作曲家は詩で用いられる言語や詩作法の特徴を活かして作曲しようとし、歌い手は詩のフレーズやリズム、意味などによって表現を紡ぐことから、ピアニストも詩に敏感に、表現(弾き分け)を考えていくことになります。
イタリア語とドイツ語のそもそもの響きの違いもありますし、イタリア人が言葉に凝縮したイメージ(シニフィアンとシニフィエの関係性)と、ドイツ人のそれとも大きく異なります。イタリア語の子音は母音の流れ(フレーズ)を干渉しないのに対して、ドイツ語では、例えば「geschwind」のように子音が大活躍するような単語も少なくありません。子音の響きが豊かな言語だとも言えますね。
この質問について、書き始めると止まらないのですが、それぞれの言語の音声学的な特徴や、文法といった言語学的な特徴、そして詩作法や詩として何が表現されているのかということに加えて、作曲家がその詩からどのような音のイメージをもって作曲したのか、作曲家は詩のどこにフォーカスして作曲しようとしたのかということなどを多角的に考え、では「演奏する私はどういう音をつくっていこうか」という思いで、イタリア語とドイツ語の歌曲を表現(弾き分け)をつくっていきたいと個人的には考えています。もちろん、歌い手の方との対話によって、表現がどんどん変わっていくこともとても大切なことですし、作品のイメージがぐっと深まったり、広がったりもします。それがアンサンブルの素晴らしいところです。
質問5
歌曲演奏時は直立不動で歌うことが多いのでしょうか?…
2022.04.25

2022年8月3日(水)14時開演
一部の演奏予定曲の解説と演奏動画
あなたは虚しく祈る
(作曲:トスティ 詩:ダンヌンツィオ)
トスティ作曲の連作歌曲《アマランタの四つの歌》の第3曲目です。心が砕け喘ぐように救いを求めますが、それを聞き入れてくれる神はいません。
セレナーデ
(作曲:コルンゴルト 詩:アイヒェンドルフ)
コルンゴルト作曲《6つの素朴な歌曲》からの一曲。若者の歌うセレナーデを傍に、ある詩人は、若かりし時の自分を重ね、若者に人生を謳歌するよう切に願っています。
やけっぱちの恋人
(作曲:ヴォルフ 詩:アイヒェンドルフ)
ヴォルフ作曲の《アイヒェンドルフ歌曲集》からの一曲。恋に破れた若者の夢想は尽きません。今、彼が望んでいることと言えば、広々とした大空のもとで横になっていたいだけ…
かわいい口もと
(作曲:トスティ 詩:ダンヌンツィオ)
ナポリの海と空が目の前に広がるかのようなピアノにのせて歌われるメロディは清らかで、甘くささやかれるようなことばもイタリア的です。…
2019.07.15

リートの魅力とは…?
音と言葉。音楽と詩と。―それぞれ異なった二つの世界であり、違った源泉から流れ出た二つの大きな流れです。しかもこの二つは、―その他のさまざまな芸術とは違って―恋愛的な同棲生活を営むこと、この二つが合体して一つの巨大な流れをなすことができます。 『音と言葉』(フルトヴェングラー著、芳賀檀訳)より 小田石崎先生はリサイタル等で積極的にリートをお歌いになられていると感じており、また先日「コルンゴルトの夕べ」(2018年6月、松尾ホール)でご一緒させていただいた際には、一言でいうと、リートへの愛がすごい!と感じました。そんな想いもあり、石崎先生にとって「リートを歌い続ける魅力」についてもぜひお聞かせいただきたいです。 石崎そうだね…、バラードとかを考えると「すべてを担える喜び」っていうのかな、単純に。それがもしオペラだったら登場人物が分かれるわけじゃない。それを1人で演じることのできる喜びっていうのかな。 小田吟遊詩人のような…? 石崎そうそう、吟遊詩人になれるっていう…、それがやっぱり醍醐味かな。それで語れる、詩もある。詩を音楽にのせて語れるっていうのがとても心地よい。 小田それはトゥルバドールの喜びに近いのでしょうね。ただそうなると、なぜイタリアやフランスの歌ではなくドイツの歌だったのか、というところも気になるのですが…。 石崎そうだよね。(現代の視点から見ると)イタリアはオペラの歴史が色濃く、もちろん歌曲もあるけど、それは「見直されてきた」という風に思う。例えば、森田学さん(声楽家)が関わられたN. v. ヴェストラウト(作曲家/1857-1898)の取り組みをはじめとして、イタリア歌曲の価値が少しずつ見直されてきたことで、いま、うまく価値が分離し始めたのがイタリアなのかな、と僕は思ってるんだよね。ドイツは、もちろんオペラやオペレッタというジャンルはあるんだけど、それとは別に歌曲というジャンルもあった。もちろんイタリアにも歌曲というジャンルはあったんだけど、明らかにウェイトはオペラにあって、それゆえに素晴らしい歌曲作品もクローズアップされにくい状況があるんじゃないかな。ドイツはクローズアップされやすい状況があった、っていうことかな。 小田1人で全部担える、ということと、国としての歴史的な系譜を考えるほかに、イタリアはオペラ、ドイツはリート、フランスはどっちも、という私たち日本人が勝手に描いているイメージはあるのかなと感じました。ドイツにもたくさん素晴らしいオペラがありますから、このイメージはあくまでもイメージでしかない、ということはありますね…。イタリア歌曲についても大変造詣が深い森田さんとお話をさせて頂く中で、どうしてもイタリアものだと歌曲だけを勉強するというイメージがない、という話をしてくださり、とても印象的だったのを覚えています。イタリアではやはりオペラが1番で、歌曲は2番目?と映ってしまってもしょうがない現状がつくり出されてしまっているのに対して、ドイツはオペラもリートも2番ではない、という状況は面白いと感じています。少し話題が飛ぶのですが、チマーラ歌曲集(全音楽譜出版社)の編纂やプッチーニ自身による自作の解釈をおまとめになった御本を出されている三池三郎先生のレッスン伴奏に伺った際に、「イタリアの歌は清潔でなければならない」とのお言葉があり、これは例え詩の内容がどんなに悲劇的でも声が感情に溺れてはならない、と私は解釈しました。一方、ドイツでは感情美学の系譜があり、H. ヴォルフ(作曲家/1860-1903)以降の作品に直接みられるように、リアルな語りの要素を歌に取り込んでいくスタイルはより声に対する美意識を拡散させたと感じています。このような背景に対し、演奏者としてどのようにリート作品と向き合い、演奏していくのかという点についてお聞かせいただけると嬉しいです。 石崎僕はドイツリートの発声や表現について概念を覆されたのはH. プライとF. ヴンターリッヒ(テノール/1930-1966)で、まぁあの時代って、例えばH. プライとF. ディースカウ(バリトン/1925-2012)、F. ヴンダーリッヒとP. シュライヤー(テノール/1935-)、この4人が4者4様で比べられていたかと思うんだけど、「ドイツリートってこうあるべきだ」という概念がまず発声としてはヴンダーリッヒに覆されたかな。これでいいんだって妙に納得した。表現で覆されたのはプライ。どうしても日本でのイメージではディースカウが強くて、僕にとっては驚きだった。なので、この2人のリートを聴いて、単純にかっこいいと思ってしまったんだよね。これがなかったらリートをやろうって思えていなかったかもしれない。 小田もう1つ視点を広げると、僕はピアノを弾く立場として、アンサンブルという側面はドイツリートの魅力を語るうえで無視できないと感じています。例えば、F. P. トスティ(作曲家/1846-1916)はとりわけその晩年、詩の持つ世界観を歌唱旋律優位にならずピアノも含めて大変繊細に表現したと感じていますが、そのような取り組みの原石は、実はもう少し早い段階でドイツでは実験されていたのではないかと感じています。ドイツでは音楽修辞の発達など、歌唱旋律の心地よさ以外の声楽作品の価値が認められやすい土壌があったのも影響があるのかもしれませんが、その中での彼らの発見の1つは「関係」、つまりアンサンブルということだったのではないかと考えています。 石崎なるほど。ドイツのなかでもいろいろあるとは思うけども、大前提は「平等」だよね。並走していくというか。並走の喜びというのは、詩が音と密接に絡み合っているのが前提として、それをピアニストと一緒に共有できる喜びだと思うんだよね。詩と音の関連を見出さず、音だけを見て伴奏合わせをするパターンもなくはないと思うけども、そこで得られる喜びと、歌い手とピアニストが一緒になって詩を見つめている喜びは違う体験だと感じるかな。そのための歩み寄りがとても緻密にできるのがリートなのかなって思うし、そこで生まれる化学反応こそリートの醍醐味かな。 小田今お話をお伺いしていて、リートの枠を考える際に、歌い手とピアニストとの関係というものも入れていいのかなと拡大解釈かもしれませんが感じました。作品そのものがリートのスタイルかどうか、という問題にとどまらず、演奏も含めて考えてみたいということです。例えば、「リートを聴けた!」という瞬間はとても貴重な瞬間だと思っていて、ピアニストが歌い手に完全についていくパターンを思うと、これはリートなのか?って考えてしまう自分がいます。やっぱり「歌」というものを考えるにあたって、演奏を一緒に成立させる、という意味では「関係的なところ」を考慮せざるを得ないと思っていて、さらに言うと、日本人は相手に合わせるのが得意なのではないかなって思ってしまいます。やはりドイツの文化の中で生まれた「リート」というものは、一人一人の関係性がイーブンであり、お互いを尊重し合い、それでいても自分の柱は持っている、という彼らだからこそこの文化が発達してきて、それをいま日本で「リートをやろう!」となると、そこがどこか欠落しがちなのではないかと感じます。
「正確な音が鳴ればリートなのか?」と思うと、少し寂しい気がします。ピアニストと歌い手は異なる旋律を持つんだけれども、詩というもので繋がることができるならば、結果としてCDのような演奏でなかったとしても、リートという現象はそこにはあるのではないか、と思います。リートとは関係的であって、ドイツ人の文化そのものである。そして、それぞれの作品は作曲家によって歌い手とピアニストの関係が試行された1つの結晶、という風に捉えてみると、リートの1つの縦断的な視点が得られる気がしますし、リートを演奏する上で大切なことってなんなんだろうか、というヒントも得られる気がしています。 石崎もう、大賛成です。例えば、教育的経験でいくと、レッスンのとき、よく、「合わせをしてきました」と言う学生がいて、「どのようにやってきたの?」と聞くとやはり縦をあわせて、音を合わせてきたみたいだったんだよね。そのときはピアニストに「歌い手の詩を語るエネルギーの流れと息の流れをきいてごらん」と言ったらうまくいってしまうんだよね。曲によっては、いくら縦を合わそうとしても合わない曲っていうのがあって、そういうところが上手く弾けるピアニストというのはアンサンブルができる準備ができているんだと思うんだよね。そういう人は、室内楽のような他ジャンルにいったとしてもうまくいくことが多いと思う。 小田自分一人がうまく演奏できたつもりでもなにか物足りない、そんなとき、「関係/アンサンブル」というものを身体は欲しているのかもしれませんね。詩と音楽のように、歌い手とピアニストも関係的であることが大切なんだ、とすごく納得してしまいました。
石崎 秀和(バリトン)
日本大学芸術学部音楽学科声楽コース卒業。ウィーン国立音楽大学リート・オラトリオ科修了。東京藝術大学大学院博士後期課程修了。修了時に博士号(音楽)を取得。文化庁派遣芸術家在外研修員として一年間ウィーンに留学。
オーストリア、バーデン市にてドナウレンダー国際夏期アカデミーコンクール第1位、第14回友愛ドイツ歌曲コンクール第3位、第11回日本モーツァルト音楽コンクール第3位等受賞。 オペラでは、新国立劇場『アンドレア・シェニエ』フレヴィル、『サロメ』カッパドキア人、びわ湖ホールオペラ『シチリア島の夕べの祈り』ベトゥーネ卿、『十字軍のロンバルディア人』アッチャーノ、読響定期『午後の曳航(世界初演)』首領、二期会オペラ公演『カプリッチョ』オリヴィエ、『魔弾の射手』キリアン、東京室内歌劇場『卒塔婆小町』詩人、『インテルメッツォ』商工業顧問官、東京・春・音楽祭『ファルスタッフ』フォード、TIAAオペラ『ヘンゼルとグレーテル』ペーター、調布市民オペラ、君津市民オペラ『カルメン』モラレス、東京シティオペラ協会『ラ・ボエーム』マルチェッロ、『魔笛』パパゲーノ、『フィガロの結婚』フィガロ、日本演奏連盟創立50周年記念事業『三人の女達の物語』町人等に出演。
オラトリオでは、バッハ「マタイ受難曲」「クリスマス・オラトリオ」、ハイドン「パウケンミサ」、モーツァルト「レクイエム」、「ハ短調ミサ」、ベートヴェン「第九」、フォーレ「レクイエム」等のソリストとして多数出演。
歌曲のリサイタルやコンサートも精力的に行っており、特にカール・レーヴェのバラードやエーリッヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトの歌曲を好んで演奏・研究している。
現在、東京学芸大学准教授。日本演奏連盟、二期会会員。…
2019.07.15

「リート」の枠を再考する
内面的で個人的な自己告白的な表現形態としてのリートの伝統、[…]、シュトラウスの<4つの最後の歌 Vier letzte Lieder>(1948)が,このジャンルにとって
文字どおりの最後のリートとなったといえるだろう。 『ニューグローヴ世界音楽大辞典』「リート」の項より 小田石崎先生、お忙しい中お時間を割いていただき、またこのような企画にお力添えくださりありがとうございます。ここでは「歌談」と題して、演奏者であり教育者である石崎先生と、定期的に「歌」にまつわるいろいろなお話をさせて頂けると嬉しいです。またこの「歌談」では、何か達成感のある着地点を前提としたトークというよりも、もう少し自由に進めていきたいです。 石崎よろしくね。 小田歌談の最初のテーマとしては、先生が大切にされているジャンル「リート」の話題からスタートできれば嬉しいです。
まず、リート(Lied)というと、いくつかすでに言われている枠(定義)があると思っていて、例えば有節歌曲形式のものをリートという、とか、民謡など民衆に近いものをリートという、など。また、ブラームス(1833-1897)はリートの理想は民謡であると言ったようで、リートってこういう方向を向こうね、というベクトルの提案を行ったと思います。 石崎そうだね。 小田いくつかの本を見ていくと、リートという言葉は多様な解釈が可能だと感じていて、リートってこうも捉えられるんじゃないか、という議論は尽きないと思うのですが、この点、石崎先生はどうお考えでしょうか? 石崎難しいよね。例えば、芸術歌曲の位置づけとして、R. シュトラウス(作曲家/1864-1949)の時代が終わって、A. ツェムリンスキー(作曲家/1871-1942)、A. シェーンベルク(作曲家/1874-1951)、A. ベルク(作曲家/1885-1935)も含めて良いのか、と言い始めると、E. W. コルンゴルト(作曲家/1897-1957)も入れたくなってしまう。むしろ、リヒャルトの本当の後継者はコルンゴルトだと個人的には言いたくなるぐらいだし、時代に隠れた作曲家としてC. レーヴェ(作曲家/1796-1869)の位置も考えたいと思っています。つまり、歌曲と呼ばれるものすごく大きな枠組みの中でリートを考える時には、俗に言われる”系列”にヒントがあるのではないかと思っています。なので、コルンゴルトが書いた歌曲作品と、例えばオペレッタ作曲家が書いた歌曲作品というのは、またちょっと変わってくる印象があります。 小田なるほど。”系列”というのは確かにあると感じました。 石崎いわゆる音楽史的に決まったレールがあるよね。例えば、リートは古典派以降、ロマン派以降など、どういう分け方だとしてもそこには枠があって、今は、その枠を取っ払ってもう一度リートを考えたいという想いがあるかな。
それを考えるきっかけになったのは、ヘルマン・プライ(バリトン/1929-1998)のLPの、確か20何枚組かな?、それはミンネザング*から現代の無調のところまで全部網羅したものだったんだよね。それは自分の中でレパートリーの基軸になってるかな。
それこそ、F. グルダ(ピアニスト/1930-2000)が作曲したドイツ歌曲もふくまれていて、実験的な曲だとは思うんだけど、詩はスタンダードでポピュラーではないし、でもリートのラインに入っちゃうんじゃないかな、と感じたんだよね。だからなにか、音楽史に捉われない流れでリートというのはあるんじゃないかな、と僕の中では思っています。 *ミンネザング…12~14世紀のドイツ語圏にて、主に「愛」をテーマとしてミンネゼンガ―によって作詩・作曲された歌のこと。
ミンネゼンガーのような吟遊詩人は後にマイスタージンガー(職匠歌人)へと繋がっていく。 小田ちなみに、A. ヴェーベルン(作曲家/1883-1945)とかそれ以降の作曲家って、僕はリートだと思ってましたけども、違うって見方もあるんですよね。 石崎そうなんだよね。無調や十二音階になったらそれは「果たしてリートか?」って話しだよね。 小田それに関しては、詩の伝統的なスタイルと、(表現は難しいですけど、)それに付する音楽も伝統的なスタイルで書かれたものが合致して初めてリートになる、という考え方なんですかね。
だから、調性が機能していて、詩の内容に則した音楽が付されているとか、何かしらの条件が整ったものをリートだと狭義の意味で定義した場合に、それに外れるものがたまたまヴェーベルンたちだった、という意見もあるかもしれないということなんですね。 石崎そうすると、少し強引かもしれないけれども、その人その人の解釈が成り立つ、とも言えるよね。そうした場合に、もう少しフリーな形でリートを捉えられると、それこそレーヴェやコルンゴルトがおさまるはずなんじゃないか、と。(笑) 例えば、H. プフィッツナー(1869-1949)は個人的には同時代の作曲家の作品と比較したときに少し渋いというイメージを受けて、同時代に活躍したR. シュトラウスの影に隠れてしまっていて、でもそれを現代を生きる私たちから見たときに、同じ1つの時系列で語っていってもよいのではないか、とも感じる。それはもしかすると日本人ならではの感覚なのかもしれないけれども。個人的には、その人その人の定義があってもいいのでは、と思っています。…