memo

2019.08.12 『美しい訣れの朝』-阪田寛夫を振り返る
合唱作品『美しい訣れの朝』(阪田寛夫作詩/中田喜直作曲)の詩をより深く考えるための参考用として、阪田寛夫の言葉や谷悦子氏による彼に関する論の一部を、出典を明記の上、次に並示します。
『美しい訣れの朝』は日本を代表する女声合唱の名曲ですが、その解釈についてより深く掘り下げようとした際、中田喜直氏や阪田寛夫氏がこの作品について言及した資料は豊富とは言えません。しかし別の視点から、例えば、阪田寛夫の人生、童謡観、<子ども>に対するイメージなどを見ていくと、少し遠回りではありますが、『美しい訣れの朝』が彼の中から生まれてきたことについて納得ができるかもしれません。
まずは以下を手掛かりに、他にも資料を探すきっかけにしてもらえると幸いです。
『童謡でてこい』(1986,河出書房新社,阪田寛夫)
「私は今から六十年前、大正の終わりに大阪の街で生まれた。町といっても、新しく市域に入れられた南のはずれである。私が子供だった昭和の初め頃から、畑や野原をつぶして家が建ちはじめ、広い道がつき、中学に進学した十年代の初めには、ほぼ空地がなくなって市街地になっていた。父は町工場の経営者で、大正の終りに土地を買って家を建てたキリスト教徒であった。新開地に生まれたキリスト教徒の子供ということが、多分私の耳に入る音楽を規制した。」(「17 きよしこのよる」の項より)
「(…)「椰子の実」の作曲者は私の叔父である。そして私がもっと小さい頃にうたった童謡はこの叔父の作品が圧倒的に多かった。(…)叔父の作ったメロディーは、完全に標準語のアクセントの高低に副って書かれていた。(…)戦後の童謡で、たとえば「ぞうさん」、「サッちゃん」などは、言葉を文字ではなく音として自律的にとらえる配慮から、だいたい標準語アクセントに副って作曲されている。しかし、戦前にはそういう近代的な言語感覚で書かれた童謡は、珍しい。叔父は山田耕筰の忠実な弟子であったから、その珍しくてむずかしい仕事を一所けんめいにやったのである。(…)叔父の童謡で変わっていたのは、その詩がほとんど素人の作品だという点だ。素人どころか、五歳とか三歳の子供の詩なんかに、叔父は一緒けんめいしゃれた曲をつけている。(…)理屈好きの大人の目で見ると支離滅裂の歌詞だが、子どもの頃の私には結構よく通じて、たのしめる歌だった。それは恐らく、叔父の曲が、詩を書いた子の空想力と同じレベルで音の世界を駆けめぐっているからこそ、こんどはそれを歌う子供の空想力をかき立てる力が生じたのだと思う。(…)ところがある日、「椰子の実」を書いて叔父は一躍名を挙げた。(…)子供の空想力をつき動かすあの空に駆け行くような童謡を、それ以降叔父は書かなくなった。(…)「椰子の実」のせいだとは思いたくない。有名になったせいでもないだろう。むしろ、気まぐれな童謡の神さまが、数年間だけ無名時代の叔父の頭の上に、見えない金の環を置いてくれたと言うべきであろう。」(「18 椰子の実」の項より)
「いま小学校の音楽教科書は四、五種類あるだろうが、一年生の教材として「めだかの学校」がたいていの本に載っている。(…)作曲者の中田喜直氏に聞いたところでは、一度曲を作ってから、ある人の勧めもあって、「そっとのぞいてみてごらん」だけを二度繰返すように改めた。それがよかった、ということである。-春の野原に来て、めだかがいそうな皮をみつけた。足音を立てても、めだかは逃げる。だからそっとのぞいてみる。見えない。もう一度乗り出して、声も立てずに目だけを走らせてみる。……あ、いたいた。という時間の経過と心の緊張とが、この曲では音楽において表現されている。喋る代りに音をつけたというだけではなく、音楽でなければ表現できない「時間」及び「緊張と解決」が、せん細な感受性と技術によって、一つの曲の中に封じこめられ送致されている。小学校の新入生でもいきなり歌える単純明快な旋律が氷山の一角だとすれば、水の下にかくれて見えない大切な重心部に当るのは、ピアノの部分である。(…)[中田喜直氏は]東京音楽学校のピアノ科から、陸軍特別操縦見習士官に応募して、パイロットになり、危うく生命永らえて家に帰ったが、アメリカ占領軍のキャバレーでピアノを弾きながら作曲を始めた。ピアノ曲も書いたが、日本には歌曲が少いから、新しい歌曲集を作ろうと志した。その時考えたことの一つは、日本の歌曲はこれまでピアノはいつも伴奏に過ぎず、ピアノが歌と対等に独立して、それぞれが対応して一つの表現をするようなものが少いという点だった。外国の本格的なリードに匹敵する日本の歌曲を作ろうとする姿勢が、そのまま子供の歌にも向けられて、先ずできたのが「めだかの学校」や「かわいいかくれんぼ」であった。」(「26 めだかの学校」の項より)
「「サッちゃんはね、サチコっていうんだ、ほんとはね。だけどちっちゃいから、自分のことサッちゃんて呼ぶんだよ。おかしいな、サッちゃん」これを標準語アクセントで読んでみる。もし「サッちゃん」のふしを知っている人がいれば、声を出して歌詞を読んだ時の抑揚やリズムが、そのまま(拡大強調されて)旋律になっているのを発見されることだろう。いや、単なる拡大強調にとどまらず、旋律が子供のお喋りの調子をうまく形どって、しかもやはり旋律としての個性の強さと美しさを備えている。自分のことを言っておかしいけれども、これは作詞者も知らないで詩の中に封じこめているリズムと抑揚を外へ引っぱりだして、魅力のある歌として定着する能力もしくは言語感覚を、作曲者が持っている証拠だろう。」(「37 サッちゃん」の項より)
「合唱、というのはふしぎなものだ。そんなに上手な合唱団の子供を一人一人別にして眺めてみると、ただ音楽が好きであるというだけで、特別に声楽のレッスンを受けているわけでもないし、まずひとりで歌えば十人なみが大部分、という普通の人の寄り合いと分るのだ。大人でも同じだ。その事情は変らない。(…)こんど気を落ち着けて歌い手の顔を1人ずつ眺めてみると、もう一度私は驚かざるを得なかった。兵隊服の男たちはもちろん、どの女の人を見ても、普通の顔立ちの、満員電車やさつまいもの配給の行列で出くわす顔ばかりだったからだ。だから、がっかりしたのではなくて、一たび燃えると、とつぜん美しく哀しい「ひびき」に昇華する人たちに、私は新しい畏敬の念をしんそこから持ってしまったのである。そして、それをなしとげさせる指揮者に対しても。(…)いまも充実した児童合唱団には、団員の特別なレッスンや素養ではなくて、普通の子供をそこまで燃やせる指揮者が必要なのだと言われている。そして充実した合唱団のうた声の輝きが、こんどは作曲家を刺激して、真正面から児童合唱に挑んで傑作を書かせるという連鎖反応を生んだ。」(「43 花のまわりで」の項より)
『阪田寛夫の世界』「第五章 多面体で描かれた子供の心と言葉」(2007年,和泉書院,谷悦子著)
「ところで、阪田寛夫は、幼児期より大勢の大人や子どもたちとの関わりの中で育っている。家族構成は、熱心なキリスト教徒だった両親と兄姉、母方の祖母、住み込みで阪田の世話や家事をしていたばあやとその娘であったが、家は教会の近くに建っていて、聖歌隊の練習が行われ、日曜学校・礼拝の度に信徒とその子どもたちとの交流があった。そのような環境のせいであろうか、阪田の作品には人間が中心に描かれている。[…] こどもの<父と母とに対する思い>を阪田がこのように描くことができたのは、彼の育った家庭環境が大きく影響していると思われる。[…]戦前まで日本の家庭は封建制・家父長制が支配的であったが、阪田家は、キリスト教の愛と音楽を二本の柱とした新しい形の家庭・家族であったのだ。それゆえ、神の前では夫婦も親子も兄弟も他者もみな平等であり、愛と音楽によって結ばれているという精神に貫かれていたといえよう。この父母と寛夫との関係は、「奈良市学園町」(『わが町』講談社)という作品の最後の部分に窺うことができる。死期の近づいた父を病院で母とともに看病している様子が描かれているのだが、父が母に向かって、「ワシャナ、モウスグ死ヌルデ」「アンタハナ 世界イチノ、ビジン」と話しかけると、母は時々笑って「甘えている。」「私は床にじかに敷いたマットレスに転がって寝たふりを」しているという場面だ。」
「[…]「おかあさんをさがすうた」(『サッちゃん』国土社)は、一貫して子どもの視点・発話によって母の不在を嘆いている。「おかあさん/いないんだ/いやだなあ」「でてきてよ おかあさん」と。[…]阪田寛夫が描いたのは、母に対する<不在への不安>と<永遠に在り続けてほしい願望>という普遍的な子どもの心であった。」
『声の力 歌・語り・子ども』「童謡の謎、わらべうたの秘密」(2002年,岩波書店)
「じつは今朝起きてカーテンをあけたら朝日がさして海も光っている。ああ今日もお天気かな、しかし昼から人前で長話をしなきゃいけないけれど、うまくいきそうもないなあ、なんて思っておりましたら、突然「ゴットンゴットン汽車さんが」という歌が出てきたんです。(…)年をとると、こんな工合に、脈絡なしにむかし歌った童謡が口をついて出てくることがあります。せっかく北海道に来ながら、白秋の「この道」でも思い出せばいいのに、色の黒い機関車の歌のような、誰も知らない、さえない歌が出てきます。(…)だいたい歌詞も曲も、当たり前でどうということもない歌が多いです。もし私が童謡作詩作曲コンクールの審査員なら、ABCランクのCランクにためらわず入れるような歌ばかりです。…ということは、幼いころの私の鑑賞能力が、かなり低かったという証拠になるのでしょうか。それとも大人からじいさんになるまでの酸っぱい時間の流れのなかで、子どものころの素朴な感覚とは違う悪しきプロ風判断基準のようなものを、サビのように身に付けてしまっていて、そのサビが、むかしはまっすぐ自分の心の奥深く飛び込んできた歌も、平凡だからダメだといばってCランクに追いやってしまったのか。私にとっては由々しき問題です。」
「(…)なつかしい童謡というものは、なんべん繰り返しても飽きることがないのですね。そういう属性を持っているらしい。ちかごろ童謡は子どものものではなくて、老謡になってしまったと嘆く人がいますが、(…)繰り返しが繰り返しを呼び、なつかしさをひとしお濃く染める童謡の性質は、いまもむかしと少しも変わりありません。」(阪田)
『木下順二対話集 人間・歴史・運命』「運命と人間について」(1989年,岩波書店)
「ぼくは戦争にはいやいや行ったし、病気ですぐ病院へ入ったりで、戦争に行っても見るべきものは見てないんですが(笑)。戦争体験も、あんまり声高に誇るような人の話は信用できませんが、しかし戦争といった生命を賭した経験をしないまでも人生に終始真面目にかかわって問い続けてる人は、割合に見るべきものを見てるのかな、と思います。(…)それに関連することなのですが、旧制高等学校で私より一年上の池田浩平という方が出征して間もなく亡くなったんですが、彼は戦争に行く直前まで考え続けたことを書きつけていて、その遺稿が本になっています。私たちの年頃の男は敗色が濃くなった最後の一、二年の間にみんな兵隊にとられる運命にあったのですが、あの頃はみんなが死生観というのをさかんにいって「海までは海女(あま)もみの借る時雨かな」という俳句を、これがおれの心境だなどと自分を安心させるために話し合ったりしたものでした。」(阪田)
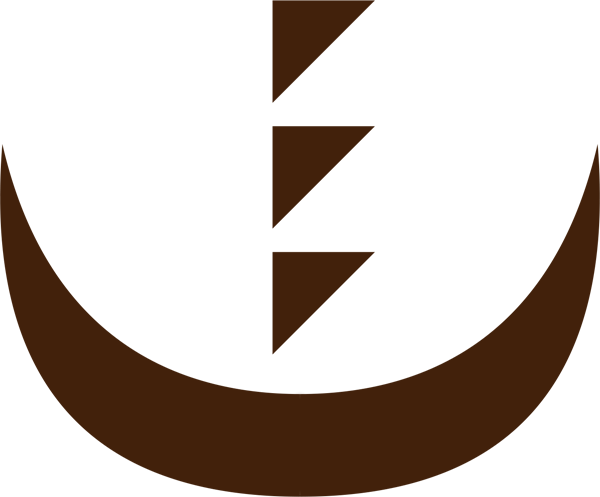


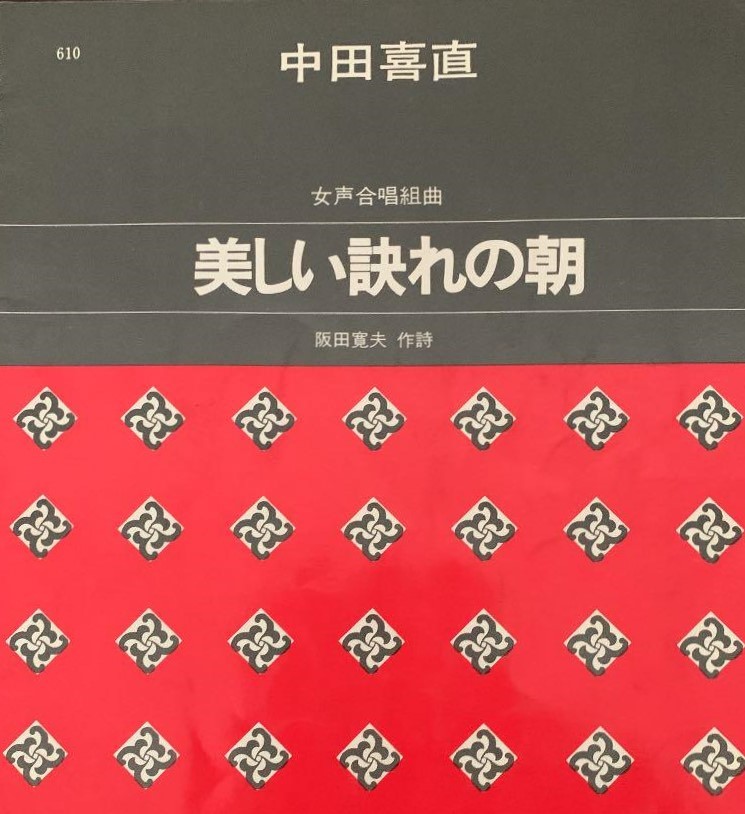
.jpg)

