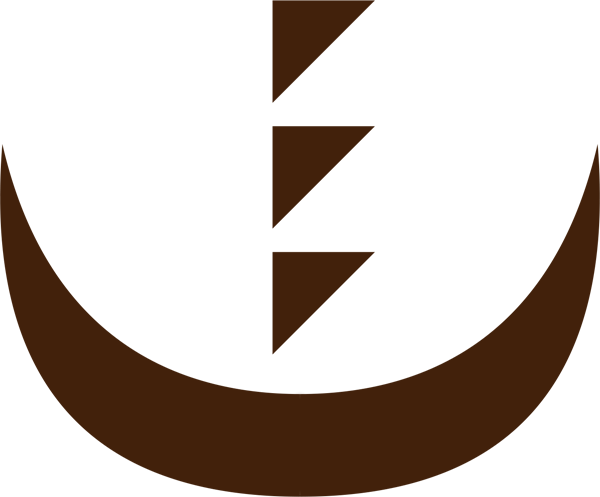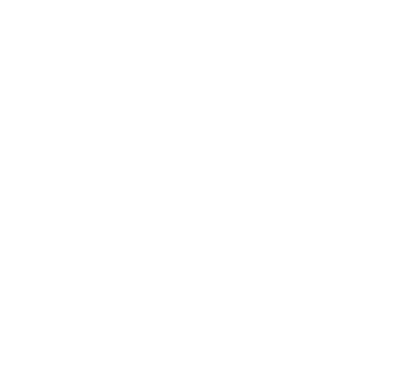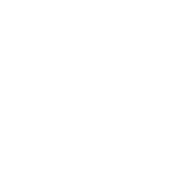news



今後の予定
詳細は随時更新していきます😌3月15日 演奏(弘前)イタリア歌曲
3月21日 演奏(青森)歌曲等のミニコンサート
3月24日 イベント(神奈川)日本歌曲
5月7日 演奏(千葉)日本歌曲他
5月17日 演奏(長野)
6月21日 演奏(東京)ロシア歌曲
7月31日 演奏(東京)日本歌曲
8月8日 イベント(弘前大学)オープンキャンパス
8月11日 演奏(東京)イタリア・ドイツ歌曲
10月下旬 学会(東京)
11月3日 演奏+公開レッスン(弘前)イタリア・ドイツ歌曲
11月29日 演奏(青森)合唱
12月22日 演奏(千葉)日本歌曲他
2月13日 演奏(青森)合唱
2月18-20日 近日情報公開…


【演奏会】杉原かおりソプラノリサイタル(弘前)
日 時:2026年3月15日(日)開 演:14:00(開場:13:30)
会 場:みちのくホール(弘前大学50周年記念会館内)
出 演:杉原かおり(ソプラノ)
小田直弥(ピアノ)
料 金:無料 *要予約
https://forms.gle/m5BspXbh6p9d4so88
備 考:本演奏会は日本学術振興会科学研究費助成事業の助成を受け、実施します。
研究題目「イタリア近代芸術歌曲,その分類と定義」(23K00111)
研究代表者:杉原かおり…


【演奏会】青森県立美術館ナイトミュージアム「花冷え」
日 時:2026年3月21日(土)19:20~19:50場 所:青森県立美術館 アレコホール
出 演:中谷久仁子(ソプラノ)
小田直弥(ピアノ)
料 金:無料
主 催:青森県立美術館
https://www.aomori-museum.jp/schedule/16550/…


【イベント】MUZAミュージック・カレッジ2025 オーボエで聴く、日本の歌と奏者の個性-イメージと表現、そして〈らしさ〉
詳細ならびにお申込みは、以下URL(ミューザHP)よりチェックください!https://www.kawasaki-sym-hall.jp/events/calendar/detail.php?id=4704…


【動画公開】炎 滝口雅子詩/西田直嗣作曲
Youtubeよりご覧ください😊https://youtu.be/QxvYA_qRb4c?si=BEp21VRfWN057E0W…


【動画公開】歌曲コンサートの今~歌物語の世界にようこそ~
2025年8月2日に実施した東京学芸大学公開講座「歌曲コンサートの今~歌物語の世界にようこそ~」から、動画を作成しました。Youtubeよりご覧ください🌞https://www.youtube.com/watch?v=6iklf5HcZTA…
works

【2024→2025】ひろさきで学ぶ 芸術歌曲の技と心
https://www.youtube.com/watch?v=14hsBUGPnH4

Ⅲ. レディ・キラア
作詩 滝口雅子 作曲 西田直嗣
作詩 滝口雅子 作曲 西田直嗣
https://youtu.be/vFeCYVXfpg8

Ave Maria
作曲 F. Schubert
作曲 F. Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=ohNyXIPRf5w

Il barcaiolo
作曲 G. Donizetti
作曲 G. Donizetti
https://www.youtube.com/watch?v=1L4lyYEDNj0
with
合唱団よびごえ
初めて合唱をする学生から高度な合唱を経験してきた学生まで、東京学芸大学音楽科学生有志で活動をしています。実践を通して「合唱×教育」を探究していきます。春こん。東京春のコーラスコンテスト2025
「クラシック・現代音楽部門(指揮あり)混声」銀賞
混声合唱のための『あい』より「あい」(谷川俊太郎詩/松下耕曲)
「Nyon Nyon」(Jake Runestad曲)
 Youtubeでも演奏を聴くことができます😊
Youtubeでも演奏を聴くことができます😊

Youtubeでも演奏を聴くことができます😊
Parlar cantando
イタリアとドイツの歌曲について、〈聴く楽しみ〉、〈歌う楽しみ〉を1人でも多くの方にお届けしたいと願って、演奏会やレッスンの企画・実施を行っています。コラボのご相談もお待ちしております!ひろさきで学ぶ 芸術歌曲の技と心
イタリアの歌、ドイツの歌を専門とする3人の歌い手かつ研究者が、歌って、お話して、レッスンを行います!11月3日(文化の日)は、弘前で一緒に、歌曲を楽しみましょう!#桜がみえる城下町で音楽研究してみた。
弘前大学教育学部音楽教育講座で行っている活動の記録です。のんびり更新していきます😌。profile

小田 直弥(おだ なおや)
香川県出身。東京学芸大学大学院(声楽領域)修了。ザクセン州立歌劇場での声楽研修、ミュンヘン国際音楽セミナーオペラ部門を修了。その際にP. Assante、古田昌子、G. Uecker、M. Gehrke各氏に音楽解釈、発声法の指導を受ける。現在は歌曲ピアニストとして演奏活動を行っており、イタリア、ドイツ、フランス、日本の歌曲に加え、イギリス、アメリカの歌曲演奏にも力を入れている。「中島康晴 オペラコンサート」(2024)、「L’univers de la belle époque: Romances sans Paroles」(2023, ソプラノ: 高橋美千子)、「大野徹也リサイタル」(2023, 2021, 2019)、「森田学バスリサイタル」(2014)等、国内外で活躍する歌手と共演する他、E. W. コルンゴルトの歌曲のみを集めた「コルンゴルトの夕べ」(2018, バリトン: 石崎秀和)等、コルンゴルトの歌曲の紹介にも取り組んでいる。「第23回 新作歌曲の会」(2023, 作曲: 岡田愛, メゾソプラノ: 小泉詠子)では、その演奏が「作品に対する理解と共感が、非常に深い次元で結実した演奏」(『音楽の友』2023年12月号)と評された。合唱指導を担当する「合唱団よびごえ」は、「合唱×教育」を探究する稀有な団体であり、コンクールでは「東京春のコーラスコンテスト2022 ユースの部 女声」で金賞・1位, 東京都合唱連盟理事長賞を受賞。https://yobigoe.com/
研究では現在、「演奏家のためのマタニティコンサート研究」(科研基盤C: 25K03770, 2025-2027年度)の他、ヤマハ株式会社との共同研究プロジェクトに参加中。これまでに、ミューザ川崎シンフォニーホール主催「ミュージック・カレッジ」2023、2024にて講師を担当する他、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ等との産学連携による教育研究など、「演奏」「教育」「研究」の3つの柱で活動を行っている。
国立大学法人弘前大学教育学部音楽教育講座ピアノ研究室助教、特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所学術フェロー、合唱団よびごえ指導者。