memo

2019.10.07 パレストリーナへの視点
現在もなお愛されているイタリア・ルネサンス後期の音楽家、パレストリーナ(正式な名を<ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina/1525-1594)>)は「教会音楽の父」と呼ばれることもあり、西洋音楽の歴史をたどっていく中で、1つのポイントとなる人物です。
ここでは、以下、パレストリーナに関して記されたいくつかの文献から、彼をめぐるいくつかの視点と、彼の代表作の1つである「Sicut cervus desiderat ad fontes」の演奏に関する記述も例示します。
「パレストリーナは、ローマ近郊の町に生まれ、一生涯にわたってほとんどローマに住み、そこで活動した。彼の関心は、事実上、専ら宗教音楽にのみ集中していた。彼は、100曲以上ものミサ曲と数百曲ものモテットを書いたが、世俗曲はほんの数曲しか作曲しなかったのである。彼は、生前にも高い評価を得ていたが、死後には、いわば、彼の時代の完璧な大作曲家として大天才の位置に列せられ、更に大きな評価を受けるようになった。彼の諸作品は、完璧な手本とされ、今日に至るまでの声楽的対位法の教育の基本となった。他に比肩するもののないほどのこうした称賛を彼が得たのは、或る程度まで、歴史的偶然の結果だったとも言える。つまり、彼は、同時代の他のとても優れた作曲家達に比べて、それほど図抜けていたわけではなかった。だが、そうとはいえ、彼の音楽は、疑いなく、典礼式用の音楽に必要とされる諸条件を見事に満たしているし、そして、トレント公会議の精神に―常に文字通りにではないにせよ―順っているのである。」
「[…]このようなパレストリーナの経歴に加えて、彼の作品のほとんどが宗教音楽であることから、彼は典型的なローマ・カトリック教会の作曲家であると言えるだろう。しかしパレストリーナは、人間的にも音楽的にも、一般に思われているほど世俗的要素を寄せ付けないような作曲家であったのではない。たとえば、世俗曲の旋律をミサ曲の素材として用いて、「ミサ戦士」という作品を書いたり、あるいは「四度のミサ」とか「無名のミサ」という不明瞭な曲名をつけることによって、世俗的素材を使用していることを隠すかのようなこともやっている。」
「彼[パレストリーナ]とともに音楽は新しい段階に足を踏み入れた。精神が音楽的素材を完全に支配し、個々の音をしっかりと捉えた。音楽は言語を映す鏡となり、言葉を語る存在としての人間を実現する能力を得た。装飾(あるいは構成)と人間表現との綜合が達成された。それによって、パレストリーナとともに音楽史上の新しい時期、すなわち人間の表現としての音楽という時期が始まったのである。」
〇ルネサンス ― パレストリーナの生きた時代
・ルネサンスという時代
「音楽史におけるルネサンスは、ギョーム・デュファイ(1400頃―74)、ジル・バンショワ(1400頃―60)、アントワーヌ・ビュノワ(1400頃―92)等、フランドル出身の音楽家たちがブルゴーニュ公国を中心に活躍し、アルス・ノヴァ以来のフランスの伝統的作曲技法を中核として、それにイギリスの充実した和声感とイタリアの流麗な旋律法とを同化することによって新しい国際的なポリフォニー様式をつくりだした十五世紀中頃にはじまり、フィレンツェのカメラータがモノディを創作することによって音楽史上のバロックを切り開いた十六世紀末にいたるまでの約一世紀半ということになる。」
「ルネサンスは、詩と音楽の『正しい』関係が真剣に論じられた時代であった。もちろん、ギリシャの芸術を手本として。しかし残念なことに、古代の音楽そのものは残されていなかった。手本にする作品そのものがないのだから、せめて理論的に古代の考え方を学ぶのが先決だった。ルネサンス人の感心なところは、いや無謀な(といった方がいいかもしれない)ところは、ギリシャ音楽と彼ら自身の音楽に、どんなに大きな違いがあるかをさして気にもとめずに、理論的研究にとどまることなく実践にものりだした点であろう。[…]この時期には言葉と音楽の関係も、今日的な見方をすれば、衒学的な迷路にまよいこんでしまったかに見える。本書が扱ってきたのは、まさにこの時期の音楽を中心としているのだ。歌詞には往々にして隠された意味があり、音楽づけは基本的に視覚的である。こうして出来あがった曲は、えらばれた者のエリート意識をくすぐる謎解きの材料となる。
1500年代も末に近づくと、プロとアマチュアの音楽家たちに、詩人や言語学者をまきこんで、新たな観点からの『正しい言葉と音楽の関係』『正しい音楽のあり方』を追求する動きがやはりフィレンツェではじまった。作曲者でもなく、演奏者でもない、第三者としての『聴き手』の立場が意識されていた点が、新しい運動のポイントの一つであった。」
「私たちは音楽を耳で聴くものと思いこんでいるが、耳に訴える曲づくりが作曲の正統派になったのは、実は1600年をすぎてからのことなのだ。たしかに、耳で聴いて感動を受ける作品はすばらしい。けれど、言葉を理解しなくても万人に感銘を与える作品のほうが、普遍的な価値を持ち、それゆえに優れているといいきれるだろうか。そんなことをいえば、聴き手の言葉の理解力に左右される声楽より、万人に同等に訴えかける器楽の方が優れている、という論議にもなりかねない。」
・パレストリーナに至るまでのイタリアの音楽
「十五世紀のイタリア人が好んで作曲したシンプルな歌曲のたぐいは、いずれもホモフォニックな三声または四声の有節歌曲である。[…]芸術的に高度な形式の詩が歌詞に選ばれるようになって、音楽面でもフロットラからマドリガーレへの決定的な第一歩がはじまった。はじめに設定した二つあるいは三つの旋律線に、詩をなんとかあてはめ押し込んでしまうという、フロットラのやり方は次第に消えていく。それに代わって一行一行の内容にあわせて音楽を新たに織り上げるようになる。すなわち、有節形式は捨てられ、通作形式が採用されるようになったのである。それとともに、歌詞の一語一語、一行一行の内容にふさわしい表現をもとめて、旋律も変化に富んだものとなっていく。もう一つの大きな変化は、ホモフォニックな様式のなかに、フランドル風の模倣的ポリフォニーが浸透していったことである。そしてまたマドリガーレの通作化から、歌詞はなにも定型詩である必要がなくなって、自由形式詩をふくむ多様な詩が用いられるようになる。」
・パレストリーナの作曲スタイル/表現
「16世紀後期のほとんどの作曲家と同様にパレストリーナは、歌詞の構文法とアクセントの型に細心の注意を払った。彼は多声的な構造の中でそれぞれの声部を、言葉のアクセントと音楽のアクセントが安定した自然な状態で一致するよう配置した」
「「クレド」の中のdescendit(天よりくだり)の例によって、すでにパレストリーナの音楽が言語を表現しながらも、同時にその一定の側面のみを反映しているということが示された。ここでは、文章構造が音楽の中に捉え込まれ、同時に表象内容の客観的側面が照らし出されている。パレストリーナにおいては、音楽はまるで自然現象のごとき感を与える。しかしそこでは、キリストが人間となったという出来事に伴う温かさ、内面性、神秘性などは、まだ音楽になっていないし、この出来事がはじめて生じたものであること、一回きりの他に類を見ないものであること、さらにはこの出来事の歴史性などの諸契機も音楽には捉えられていない。」
「クヌート・イェッペセンは、パレストリーナと不協和音に関する非常にすぐれた研究(ロンドンで1946年出版、ニューヨークで1970年に再版)において、パレストリーナの旋律線の本質の研究は、彼の様式を理解するための正しい出発点であると主張している。また彼は、この作曲家特有の息の長い旋律について『上昇・下降の運動が、ほとんど数学的な正確さで互いにバランスを保つ』緩やかなアーチをなしているもの、と述べている。すなわち、パレストリーナの優雅な音の曲線は、旋律線の滑らかな流れを妨げる何物もない状態で、大部分は順次進行と比較的わずかの反復音を伴う形で構成されており、大きな、または不自然な跳躍は見られない。」
「もし彼のモテトゥスの幾つかがその言葉の雰囲気に美しく合っているように思われるならば[…]その理由は、使われている特殊な技法の中によりも、いくつかの捉えがたいもの(おそらく、現代の聴衆の主観的な反応もそれに当たるが)の中に求めるべきである。彼の音楽が非個人的であり、精神性に満ちている、という印象を作り出しているのは、まさにパレストリーナが、彼個人の感情をあからさまに表現することで作品の穏やかな表面を乱すことを自制しているからである。」
・Counterpoint/対位法
「パレストリーナの対位法は、優雅な旋律線の形と不協和音の慎重な扱いばかりでなく、模倣技法の使い方と巧妙な和声プランによっても統御されている。彼は楽節をそのまま、あるいは変化させて繰り返したり、元の素材に新しい声部を付け加えたりして曲を作り上げることがある。またあるときは逆行対位法invertible counterpointを取り入れるとか、1つの模倣段落全体を移調する、などの理屈っぽい手法を用いる。」
・eye music/Tonmalerei/音画
「マドリガーレ作曲家達は、歌詞にみられる比喩や象徴を音楽的に表現するのに成功した。[…]『音楽的に表現する』というのは、かならずしも聴覚的に音にするということではない。『視覚的に音にする』こともその方法の一つなのだ。」
・トリエント宗教会議(1545-1563)
「イタリアにおいては、反宗教改革の時代にトリエント宗教会議が開かれて、そこで典礼音楽に関する問題も論議された。教会は音楽に対して、典礼文尊重を要求した。しかし余りにもしばしば繰り返されるこの事実よりも、次のことの方が重要なのである。すなわち、音楽言語の発展史上でパレストリーナの業績によって達成された一応の完結は、ミサの典礼としての発展史上における完結と一致するということである。これに先立つ時代、たとえば十五世紀などは、典礼の見地からみるとある種の荒廃の時期だった。ミサは内容的に歪められてしまい―ルターの非難がこれを物語っている―それのみかミサのテキスト自体が腐敗していた。[…]したがってトリエント宗教会議の時代には、音楽上の問題は、ミサを典礼的に新しく作りなおすことに関する多くの仕事のうちのひとつにすぎなかった。」
〇Sicut cervus desiderat ad fontes
・概説
「この4声モテトゥスは、1581年にヴェネツィアで出版された『パレストリーナ・4声モテトゥス集』第2巻に含まれるもの[…]全体は典型的な通模倣様式によって書かれており、その旋律は、パレストリーナ特融の柔らかい曲線を描いている。」
・詩について - 旧約聖書『詩編』第42編第1節 から
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum,
(~のごとく/鹿が/あえぎ慕う/~を/源泉/水の流れの)
ita desiderat anima mea ad te, Deus.
(そのように/あえぎ慕う/魂//我が/~を/汝/神よ)
・演奏について
「パレストリーナ様式の音楽には、どのような演奏がふさわしいのであろうか。[…]如何なる編成であっても、パレストリーナ様式の音楽的特質が、常に充分に考慮されていれば良いと思う。すなわち、人間の声特有の透明で温かい響き、ほぼ等しい機能を与えられた各声部間の音楽的対話が生み出す効果、音色や音量などの微妙な変化、そして、すべてが純粋であり単純であることのすばらしさ、などが実現されているかどうかが大切な事である。これらのポイントは、大合唱ではなく、少人数のア・カペラでの精緻な演奏によってのみ実現が可能となる。」
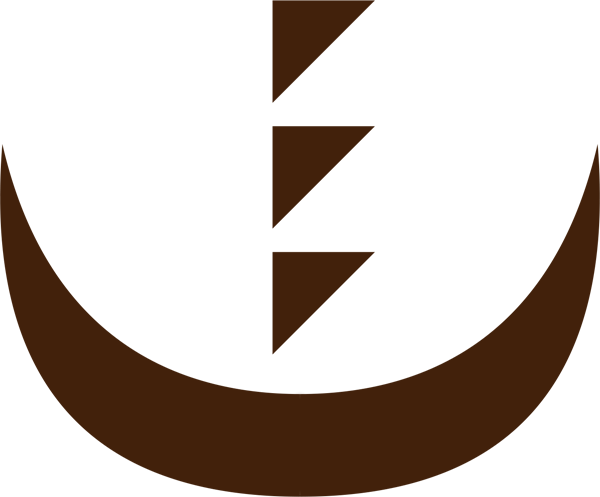


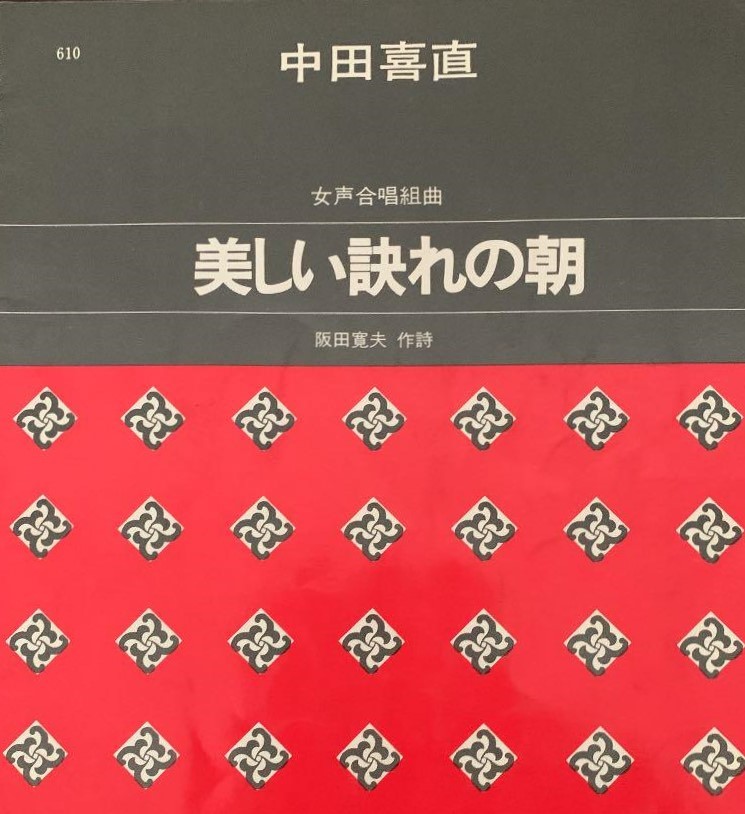
.jpg)

