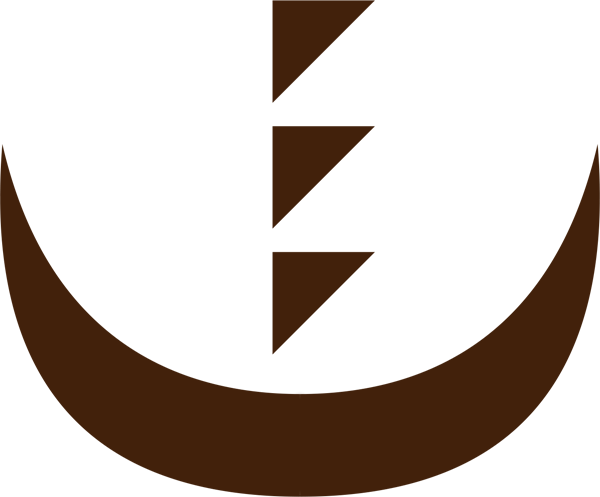uta-dan

リートの魅力とは…?
 小田石崎先生はリサイタル等で積極的にリートをお歌いになられていると感じており、また先日「コルンゴルトの夕べ」(2018年6月、松尾ホール)でご一緒させていただいた際には、一言でいうと、リートへの愛がすごい!と感じました。そんな想いもあり、石崎先生にとって「リートを歌い続ける魅力」についてもぜひお聞かせいただきたいです。
小田石崎先生はリサイタル等で積極的にリートをお歌いになられていると感じており、また先日「コルンゴルトの夕べ」(2018年6月、松尾ホール)でご一緒させていただいた際には、一言でいうと、リートへの愛がすごい!と感じました。そんな想いもあり、石崎先生にとって「リートを歌い続ける魅力」についてもぜひお聞かせいただきたいです。
 石崎そうだね…、バラードとかを考えると「すべてを担える喜び」っていうのかな、単純に。それがもしオペラだったら登場人物が分かれるわけじゃない。それを1人で演じることのできる喜びっていうのかな。
石崎そうだね…、バラードとかを考えると「すべてを担える喜び」っていうのかな、単純に。それがもしオペラだったら登場人物が分かれるわけじゃない。それを1人で演じることのできる喜びっていうのかな。
小田吟遊詩人のような…?
石崎そうそう、吟遊詩人になれるっていう…、それがやっぱり醍醐味かな。それで語れる、詩もある。詩を音楽にのせて語れるっていうのがとても心地よい。
小田それはトゥルバドールの喜びに近いのでしょうね。ただそうなると、なぜイタリアやフランスの歌ではなくドイツの歌だったのか、というところも気になるのですが…。
石崎そうだよね。(現代の視点から見ると)イタリアはオペラの歴史が色濃く、もちろん歌曲もあるけど、それは「見直されてきた」という風に思う。例えば、森田学さん(声楽家)が関わられたN. v. ヴェストラウト(作曲家/1857-1898)の取り組みをはじめとして、イタリア歌曲の価値が少しずつ見直されてきたことで、いま、うまく価値が分離し始めたのがイタリアなのかな、と僕は思ってるんだよね。ドイツは、もちろんオペラやオペレッタというジャンルはあるんだけど、それとは別に歌曲というジャンルもあった。もちろんイタリアにも歌曲というジャンルはあったんだけど、明らかにウェイトはオペラにあって、それゆえに素晴らしい歌曲作品もクローズアップされにくい状況があるんじゃないかな。ドイツはクローズアップされやすい状況があった、っていうことかな。
小田1人で全部担える、ということと、国としての歴史的な系譜を考えるほかに、イタリアはオペラ、ドイツはリート、フランスはどっちも、という私たち日本人が勝手に描いているイメージはあるのかなと感じました。ドイツにもたくさん素晴らしいオペラがありますから、このイメージはあくまでもイメージでしかない、ということはありますね…。イタリア歌曲についても大変造詣が深い森田さんとお話をさせて頂く中で、どうしてもイタリアものだと歌曲だけを勉強するというイメージがない、という話をしてくださり、とても印象的だったのを覚えています。イタリアではやはりオペラが1番で、歌曲は2番目?と映ってしまってもしょうがない現状がつくり出されてしまっているのに対して、ドイツはオペラもリートも2番ではない、という状況は面白いと感じています。
少し話題が飛ぶのですが、チマーラ歌曲集(全音楽譜出版社)の編纂やプッチーニ自身による自作の解釈をおまとめになった御本を出されている三池三郎先生のレッスン伴奏に伺った際に、「イタリアの歌は清潔でなければならない」とのお言葉があり、これは例え詩の内容がどんなに悲劇的でも声が感情に溺れてはならない、と私は解釈しました。一方、ドイツでは感情美学の系譜があり、H. ヴォルフ(作曲家/1860-1903)以降の作品に直接みられるように、リアルな語りの要素を歌に取り込んでいくスタイルはより声に対する美意識を拡散させたと感じています。このような背景に対し、演奏者としてどのようにリート作品と向き合い、演奏していくのかという点についてお聞かせいただけると嬉しいです。
石崎僕はドイツリートの発声や表現について概念を覆されたのはH. プライとF. ヴンターリッヒ(テノール/1930-1966)で、まぁあの時代って、例えばH. プライとF. ディースカウ(バリトン/1925-2012)、F. ヴンダーリッヒとP. シュライヤー(テノール/1935-)、この4人が4者4様で比べられていたかと思うんだけど、「ドイツリートってこうあるべきだ」という概念がまず発声としてはヴンダーリッヒに覆されたかな。これでいいんだって妙に納得した。表現で覆されたのはプライ。どうしても日本でのイメージではディースカウが強くて、僕にとっては驚きだった。なので、この2人のリートを聴いて、単純にかっこいいと思ってしまったんだよね。これがなかったらリートをやろうって思えていなかったかもしれない。
小田もう1つ視点を広げると、僕はピアノを弾く立場として、アンサンブルという側面はドイツリートの魅力を語るうえで無視できないと感じています。例えば、F. P. トスティ(作曲家/1846-1916)はとりわけその晩年、詩の持つ世界観を歌唱旋律優位にならずピアノも含めて大変繊細に表現したと感じていますが、そのような取り組みの原石は、実はもう少し早い段階でドイツでは実験されていたのではないかと感じています。ドイツでは音楽修辞の発達など、歌唱旋律の心地よさ以外の声楽作品の価値が認められやすい土壌があったのも影響があるのかもしれませんが、その中での彼らの発見の1つは「関係」、つまりアンサンブルということだったのではないかと考えています。
石崎なるほど。ドイツのなかでもいろいろあるとは思うけども、大前提は「平等」だよね。並走していくというか。並走の喜びというのは、詩が音と密接に絡み合っているのが前提として、それをピアニストと一緒に共有できる喜びだと思うんだよね。詩と音の関連を見出さず、音だけを見て伴奏合わせをするパターンもなくはないと思うけども、そこで得られる喜びと、歌い手とピアニストが一緒になって詩を見つめている喜びは違う体験だと感じるかな。そのための歩み寄りがとても緻密にできるのがリートなのかなって思うし、そこで生まれる化学反応こそリートの醍醐味かな。
小田今お話をお伺いしていて、リートの枠を考える際に、歌い手とピアニストとの関係というものも入れていいのかなと拡大解釈かもしれませんが感じました。作品そのものがリートのスタイルかどうか、という問題にとどまらず、演奏も含めて考えてみたいということです。例えば、「リートを聴けた!」という瞬間はとても貴重な瞬間だと思っていて、ピアニストが歌い手に完全についていくパターンを思うと、これはリートなのか?って考えてしまう自分がいます。やっぱり「歌」というものを考えるにあたって、演奏を一緒に成立させる、という意味では「関係的なところ」を考慮せざるを得ないと思っていて、さらに言うと、日本人は相手に合わせるのが得意なのではないかなって思ってしまいます。やはりドイツの文化の中で生まれた「リート」というものは、一人一人の関係性がイーブンであり、お互いを尊重し合い、それでいても自分の柱は持っている、という彼らだからこそこの文化が発達してきて、それをいま日本で「リートをやろう!」となると、そこがどこか欠落しがちなのではないかと感じます。
「正確な音が鳴ればリートなのか?」と思うと、少し寂しい気がします。ピアニストと歌い手は異なる旋律を持つんだけれども、詩というもので繋がることができるならば、結果としてCDのような演奏でなかったとしても、リートという現象はそこにはあるのではないか、と思います。リートとは関係的であって、ドイツ人の文化そのものである。そして、それぞれの作品は作曲家によって歌い手とピアニストの関係が試行された1つの結晶、という風に捉えてみると、リートの1つの縦断的な視点が得られる気がしますし、リートを演奏する上で大切なことってなんなんだろうか、というヒントも得られる気がしています。
石崎もう、大賛成です。例えば、教育的経験でいくと、レッスンのとき、よく、「合わせをしてきました」と言う学生がいて、「どのようにやってきたの?」と聞くとやはり縦をあわせて、音を合わせてきたみたいだったんだよね。そのときはピアニストに「歌い手の詩を語るエネルギーの流れと息の流れをきいてごらん」と言ったらうまくいってしまうんだよね。曲によっては、いくら縦を合わそうとしても合わない曲っていうのがあって、そういうところが上手く弾けるピアニストというのはアンサンブルができる準備ができているんだと思うんだよね。そういう人は、室内楽のような他ジャンルにいったとしてもうまくいくことが多いと思う。
小田自分一人がうまく演奏できたつもりでもなにか物足りない、そんなとき、「関係/アンサンブル」というものを身体は欲しているのかもしれませんね。詩と音楽のように、歌い手とピアニストも関係的であることが大切なんだ、とすごく納得してしまいました。

石崎 秀和(バリトン)
日本大学芸術学部音楽学科声楽コース卒業。ウィーン国立音楽大学リート・オラトリオ科修了。東京藝術大学大学院博士後期課程修了。修了時に博士号(音楽)を取得。文化庁派遣芸術家在外研修員として一年間ウィーンに留学。
オーストリア、バーデン市にてドナウレンダー国際夏期アカデミーコンクール第1位、第14回友愛ドイツ歌曲コンクール第3位、第11回日本モーツァルト音楽コンクール第3位等受賞。